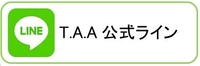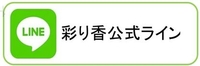- ホーム
- 3月は『夢宵桜』(ゆめよいざくら)
3月は『夢宵桜』(ゆめよいざくら)
2021/02/28夢宵桜
2021/2/28
十日町織商さんが
1981年に制定された12ヵ月の季の色では
3月は「夢宵桜(ゆめよいさくら)」
こんな色です。

今でこそ、花見といえばサクラですが、花見の最初は梅の花を愛でるといったものでした。
桜が、大人気になったのは江戸時代。
8代将軍吉宗なども、さかんに桜を植えたとの記録が残っているそうです。
それは、植樹をすることで土手を強化しようとする施策のひとつだったとか。
落語「長屋の花見」などを聞いても、桜の花見が庶民の楽しみであったことが伺えます
「宵っ張りの朝寝坊」とか
「まだまだ、宵の口!もう一軒、飲みに行こう」
なんて言ったりすることから、夜の遅い時間だと思いがちですが、
実は「宵」というのは、日が暮れてまだ間もないころ、なのです。
江戸時代は、時間の観念というものが、庶民の間にも広まった時代です。
武士は参勤交代で江戸とお国を行き来していましたが、その出立の時刻も決められていました。
庶民においても、長屋の木戸が閉まる時刻までには、家に帰っていなければなりません。
とはいえ、その頃は今のような精巧な時計が出回っていたわけではなく、日の入りと日の出が基準となりました。
だから、冬と夏とでは、1時間の長さが違うんです。
驚きですよね。
桜色というのは、紅梅色よりずっと薄いピンクです。

まるで、「ここに花が咲いてるよ!わたしはここよ!」と主張するのが梅だとすると
「咲いている私を観たいなら、どうぞ」
といった、ちょっとクールな美しさを持つ桜。
「宵待桜」という色名は、暖かい陽気に誘われて、昼間にわーーっと多くの花を咲かせてしまった自分を恥じるように、夜の闇を待っているような情景が浮かびます。
そして、夜になってしまうと、漆黒の闇の中、月の光に浮かぶ白っぽい桜の花びらは、何やら怪しげな空気を漂わせます。
いにしえの頃、
桜は、山の神様が里に下りてきて、田植えに適した時期を教えてくれる「依り代」でした。
「樹齢を重ねた桜の木の根元には、死人(しびと)が埋まる」
なんてことを、聞いたことはないですか?
神が宿る木ゆえに、だれも粗末に扱わないことが、桜の気高さに繋がったのかもしれませんね。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
来月の「虹いろのお話し」は、「花舞小枝」です。
どんな色だとおもいますか?どうぞ、お楽しみに!